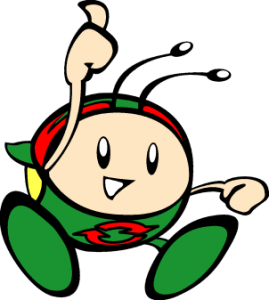

青空学

近代工業都市となった北九州市で公害が起こってからSDGs未来都市となった現在までの
北九州市の環境史を専門的に整理。
よくある質問や「北九州市史 市政編(平成29年3月発行/北九州市)」に対応した充実の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=w4PI_tsPNw0&t=149s2015年から行ってきた、環境ミュージアム館長の中薗哲による、北九州市の環境への取組みの歴史をお話しするミニセミナー「青空学」。
環境局OBである館長にしか語れない数々のエピソードが、バーチャルミュージアム内で公開されます!
北九州市の環境史を学びたい方必見のページです。
青空学について、館長から皆様に贈るメッセージをお届けします。
青空学概要
~伝えたい地域の歴史とSDGs~
明治時代から日本の近代化の一翼を担ってきた北九州は、第二次大戦後、国土の復興を牽引する役割を果たした。
その後、日本全体の経済発展のなかで相対的な地位は低下したが、今再び、環境未来都市として持続可能な循環型社会のあるべき姿を指し示す大きな役割を果たそうとしている。
大きな転換が実現した背景には、「青空がほしい」に始まる公害との戦いから、様々な課題に積極的に挑戦し克服してきた過程があり、産官学の連携に市民が積極的に参画してきたことの成果が生きている。
いまここで、成果を挙げつつある環境政策の成り立ちを振り返り、何を伝え、何を引き継いでいくべきか考えてみることには大きな意義がある。何を伝え、何を引き継いでいくかにより、北九州の未来は大きく変わるだろう。
いくつもの課題を見出し、挑戦し、克服してきた過程で、どのような主体が関わり、どのように考え、どのように克服してきたのか、そしてそれが何をもたらしたのかということを知り、そこに流れる北九州市民としての、企業、市民、行政、学術機関の情熱とその果たした役割を掘り起こし、未来世代に伝えていかねばならない。
過去の客観的な事実としての歴史は、すでに北九州市公害対策史をはじめ、文献資料として整理されているが、テーマを設定してストーリー展開することにより、各種資料とミュージアムの展示とをつなげることができれば、伝えるべきこと、引き継ぐべきことを明確なメッセージとして残すことができる。
令和2年6月
北九州市環境ミュージアム
館長 中薗 哲
1 公害の発生と克服
北九州市環境ミュージアムの隣に、白い巨大な溶鉱炉が保存されている。
その場所に1901年官営八幡製鐵所の最初の溶鉱炉が建てられた。溶鉱炉はほぼ10年毎に改修を繰り返すので1901年当時の姿はとどめてないため世界遺産の対象ではないが、製鐵所にとっては心臓部にあたる重要な設備であることは間違いない。
筑豊炭田の豊富な石炭を利用して製鐵所が建設され、鉄鋼、セメント、化学という重要産業が発展、明治時代から戦後の国土復興を経て、国の発展に大きな貢献をしてきた。
一方で、鉄鋼、セメント、化学工業や発電所は、たくさんのばい煙や排水を排出する産業であり、北九州地域は深刻な公害を経験した。
洞海湾は「死の海」となり、空は「七色の煙」でおおわれていた。
30年ほど前まで、北九州市は「公害の街」、「灰色の街」と呼ばれ、市民の間でも「住みたくない街」と言われていた。現在では「環境先進都市」として国内外に知られ、SDGsモデル都市として世界をリードしている。
この間に誰がどのように努力してきたのかを伝えたい。歴史を学ぶことでSDGsの未来が見えてくる。

(2)北九州市の自然・地理
一方で、北九州は緑が多く自然の豊かな地域でもある。瀬戸内海側には曽根干潟が広がり、カブトガニの産卵など自然を生かした環境教育の場となっている。
響灘側には広大な埋め立て地の中に、貴重な動植物が棲みついた響灘ビオトープがあり、多くの市民が自然を楽しむために訪れる場所となった。内陸側には山田緑地、合馬の竹林があり、カルスト台地の平尾台が広がっており、平尾台には、ラムサール登録を目指す湿地がある。
産業面では、日本製鉄だけではなく、世界的企業としてなじみ深いTOTOの本社が小倉にある。ロボットで有名な安川電機の本社が黒崎にある。北九州市に隣接した地域には、トヨタ自動車、日産自動車の工場もあり、産業ポテンシャルの高い地域であることがわかる。
響灘には白島洋上石油備蓄基地があり、560万キロリットルの原油が備蓄されている。国内に石油資源のない日本は輸入に頼っているが、万一輸入が途絶えた時の備えとして建設されたものだ。日本全体で使用する石油の約16日分がここに備蓄されている。
(3)北九州の変遷
初期の主力製品はレールで、鉄道を整備して産業の発展を図っていった。レール工場は100年以上を経た現在でも現役工場として生産を続けている。現在は新幹線のレールが作られている。
製鉄所ができると、セメントや化学、電力などの関連工場が次々とつくられていった。
1968年に5市が合併して北九州市が誕生したが、高度経済成長が始まった時期でもあり、深刻な公害に見舞われていた。北九州市の歴史は、公害の歴史と重なっているといえる。
当時は日本国中で公害問題が発生していた。特に水銀による悲惨な水俣病が大きな社会問題となっていた。新潟でも同じ水銀中毒が発生した。2度の失敗を経て、日本では現在水銀に関して厳しい管理が行われている。
(4)七色の煙
1950年、戦後の国土復興が本格的に始まり、電力需要の増大に対応するため石炭火力発電所が増設された。
たくさんのばいじんに見舞われた戸畑の中原地区では、婦人会が洗濯物の汚れ方など具体的な調査資料をそろえて行政、企業に働きかけて集塵機を設置させることに成功した。運動を起こすにはまず自分たちができることから始めるという考え方を示し、全国的にも公害防止運動の先駆けとなった。
戦後のベビーブームに対応して、工場地帯に城山小学校が作られた。
企業の社宅など工場で働く人の住宅があったので、子供たちの通学の利便性を考えてここに設置された。しかし、周囲は化学工場、セメント工場、製鐵所に囲まれており、どちらから風が吹いても粉じんが降ってくる場所にあり、1か月に100トンの降下ばいじん量を記録するなど、当時日本で一番たくさん降下ばいじんが降る小学校と言われた。
校舎にあった雨どいや屋根瓦には、たくさんのセメントやすすを中心とした粉じんが堆積し、流れないまま固まっていた。電線にはつららのように粉じんが固まっているのが見える。大量の粉じんが空から降ってきた。
学校には空気清浄機が設置され、子供たちはそのフィルターを洗うのが日課になっていた。フィルターを洗ったときの真っ黒い水を見て、逆に教室内ではきれいな空気がすえるということで、喘息の発作が起きにくかったという心理的効果も認められ、多くの学校に積極的に空気清浄機が設置された。
公害地域の学校ではひ弱な子供たちが育つのではないかと言われ、教師たちは様々な工夫をした。体育や音楽にも力を入れ、賞をもらうほどになった。
教師たちは公害地域における教育の在り方を研究テーマにするなど、積極的に取り組んだ。
企業では、法律による規制はまだなかった頃から、技術開発が進められ、赤い煙をなくすとともに、排ガスから燃料や原料を回収することが始まった。
(5)死の海
当時の海の様子。洞海湾は魚介類はおろか、大腸菌も棲んでないことがわかり、この海は死んだと言われた。
マスコミは「死の海・洞海湾」としてキャンペーンしたので、全国的に知られるようになった。
長い航海をした貨物船は船底にカキや貝が付着して船のスピードが落ちるので、ドックに入れてカキや貝を落とす必要があるが、洞海湾に入ると、船底のカキや貝が死んで落ちるので、ドック入りの経費が要らなかったと喜ばれた。
しかし、このスクリューのように腐食して船も相当傷んでいたと思われる。
急激な生産増加により大量の廃水が発生したことから、企業では廃水処理施設を設置するとともに、処理後の水を再利用する技術が開発された。法律による排水規制が始まるよりも前に、企業の自主的な取り組みが始まった。
排水処理が始まると、洞海湾の水は急速に改善していった。
しかし、大きな問題があった。化学工場から排出された水銀を多く含んだヘドロが海底に堆積していた。
洞海湾で水俣病が発生しなかったのは、魚介類がいなかったから。しかし、水質が改善してくると外海から魚が回遊してくるようになった。そこで海底のヘドロを浚渫することになった。
30PPM以上の水銀を含有するヘドロ35万㎥を、2年間で18億円の経費をかけて取り除いた。
ヘドロの浚渫にあたっては濁りが拡散しないように海底までフェンスを設置し、新たに開発した浚渫グラブを使用するなど最新の技術が導入され、更には、湾内で最終処分するために企業の泊地を利用するなど細心の注意が払われ、様々な環境対策が取られた。
海底のヘドロを浚渫すると、海がよみがえってきた。
現在洞海湾には、近隣の海域で見られる魚介類が棲息しており、一部の魚介類は洞海湾内で再生産していることも確認されている。
(6)婦人会の取り組み
北九州市の観光用の絵葉書やポスターに使われていた写真では、赤や茶色、黒の煙が空を覆っていた。
この煙を見て、多くの市民は北九州の空に虹がかかったと表現した。虹は幸せの象徴で、産業の発展により、豊かになると考えた。
そのような時期に、この煙は健康に害があるので、なくさなければならないと主張することは大変勇気がいる事だった。
その勇気を示した人たちがあらわれた。それは、婦人会の方たちだった。
家庭の主婦たちは、家の掃除や洗濯で公害を実感していた。洗濯物は乾くよりも前に、汚れて、洗い直すこともしばしばだった。何よりも、子供たちの健康が心配だった。工場で働く主人の健康も心配。婦人会の人たちは、まず自分たちでできることから取り組むことにした。
大学の先生に依頼して、環境の調査の仕方から勉強を始めた。自分たちで、サンプルを集めて、指導を受けながら分析もした。被害の実態をまとめて、その資料を手に行政と企業に対策を要請した。
行政と企業は婦人会の要請を真摯に受け止めて、話し合いが始まった。
婦人会は、自分たちの活動を8ミリ映画に記録して、「青空がほしい」という作品を多くの市民に見てもらった。また、調査結果を基に市民向けに講演会を開催するなどの活動の結果、多くの市民の支持を得るのに成功した。
公害問題を、関係するすべてのステークホルダーが協働して解決するという流れができたという点で、婦人会の活動は大きな意義を持つ。
公害を克服するまでには、この後も様々な対策と、長い年月を要したが、公害を克服できた時点で、市民と企業と行政の間で相互に信頼関係が確立された。
(7)公害の激化と企業・行政の取り組み
北九州市の発足により公害防止に取り組む体制の整備が進んだが、高度経済成長の進展により公害は一層激化し、1969年5月、北九州市で初めて「スモッグ警報」が発令された。
灰色の空に慣れていた市民も、亜硫酸ガス濃度が健康被害を生じるほどの高濃度であることを知り、不安と怒りが行政に向けられた。マスコミが大キャンペーンを展開したこともあり、全市一体となった公害との本格的な戦いが始まった。
行政は、風向、風速、気温などの気象観測装置を設置して、高濃度汚染が発生する恐れのある気象条件になると、工場からのばい煙の発生量の削減要請をするという制度を企業の協力も得て実施することにより、スモッグ発生を未然に防ぐことに成功した。
あわせて抜本的な対策として、風洞実験などの大気汚染予測技術を用いて、環境基準達成を目指した排出規制基準を策定して、公害防止協定を締結した。
企業は厳しい排出規制を達成するため、それまでのエンドオブパイプ対策(排出口に高性能の処理施設を設置する方法)から、クリーナープロダクション技術(省エネルギー・省資源による汚染物質の発生抑制の技術体系)への切り替えを進めた。この技術革新により、環境改善と経済性改善を両立させることに成功した。こうして、1975年には、環境基準を達成することができた。
環境基準を達成しても、市民には「灰色の街」「公害の街」というイメージが強く残っていたが、環境庁が実施したコンテストで「星空の街」に選ばれ、環境衛生研究所が実施した洞海湾の生物調査で100種類を超える魚介類が生息していることが確認されると、市民の間にようやく「青い空と海」を取り戻したという実感が生まれた。
2 環境国際協力の展開
(1)企業の取り組み
公害防止で最も苦労したのは企業だった。
生産設備よりも巨大な排ガス処理施設や、排水処理施設が建設された。これらの巨大な施設は、建設費も運転経費も巨大な額になった。しかも、これらの施設は利益を生み出すものではない。
この時、企業では技術革新が起きた。生産設備そのものを、公害発生の少ない施設に改善するという技術が開発された。
その一つの例として「省エネルギー」がある。
生産設備を省エネルギー設備に改善すると、使用するエネルギーが少なくなるだけでなく、排出ガスの量も少なくなり、処理設備はコンパクトなものになる。
環境を改善しながら、生産コストと処理コストを引き下げることができるのだ。同じ考え方は、水の使用や、原料の使用、副産物の再利用などにも、取り入れられた。
こうして、環境と経済の両立が可能になった。
しかし、生産設備を改善するためには、製造メカニズムの研究、温度やガスの管理、様々な測定システム、そしてそれらを運用する技術者の養成が必要になる。
このようにして、低公害生産技術の技術体系が確立された。
(2)国際協力
一方、オイルショックを機に鉄冷え不況に見舞われ、産業構造の見直しを迫られた結果、国際技術都市としての発展に活路を求め、国際協力事業団の国際研修センター誘致を目指して、1980年、北九州国際研修協会(KITA)が設立された。来日した研修員は、市民団体を中心としたおもてなしを受けて、日本文化に触れることもでき、北九州が大好きになって帰国していった。それぞれの国で重要な役割を果たすと同時に、日本の良さも広めてくれた。
友好都市である中国大連市からの要請を受けて環境協力を実施した。大連環境モデル都市計画として成果を上げたが、この時の経験により、環境国際協力では、都市間の協力が効果的であることを学んだ。現在、多くの都市との間で、環境協力ネットワークを形成している。
環境国際協力は、世界中の都市との都市間環境協力ネットワークに発展した。
北九州国際技術協力協会(KITA)、地球環境戦略研究機関(IGES)、アジア低炭素化センターなど、企業、行政の連携が推進されており、国の国際協力機構(JICA)の九州支部は当初福岡市に設置されたが、北九州市に移転するなど、地方の一極集中を是正することも可能となった。
環境国際協力の面では、北九州国際研修協会は北九州国際技術協力協会に改組して環境協力センターを設置し、国際協力機構や国際協力銀行その他の資金援助によって途上国の環境調査・コンサルティング事業を実施し、具体的な環境改善に貢献した。また、友好都市である中国大連市との都市間協力は、ODAの新しいあり方として国内外から注目された。
2000年に北九州市で開催されたUNESCAP(国連アジア太平洋経済社会委員会)環境大臣会議において、北九州イニシアティブが採択され、都市間環境協力のためのネットワークが形成された。
3 様々な環境政策の展開
(1)国際社会からの評価と市民意識
公害克服の実績と、その経験を活用した国際協力が評価されて、1990年、国連環境計画(UNEP)から「グローバル500」を受賞した。更には、1991年のリオサミットにおいて「国連自治体表彰」を受賞した。
このことは、北九州市民をおおいに元気づけた。国際的に注目を集め、市民にとっても環境を取り戻したという自信が生まれ、地球環境問題やリサイクルなど幅広い分野で環境問題に取り組みたいという意識が広がった。
市民の環境意識は高まり、市民は「もっといろいろなことができる」と、身の回りの環境問題に積極的に取り組むようになった。
(2)エコタウン
環境意識の高まった市民が最初に指摘したのはごみ問題。
それまで、北九州市はごみの衛生的、効率的処理を推進しており、ごみの全量焼却の体制を確立し、廃熱を利用した電力再利用も実施していた。
市民は、リサイクルできるものは回収してリサイクルすべきだと行政に要請した。この時も、市民は、「私たちはきちんと分別するから、行政は資源として再利用するシステムを構築してほしい」と、まず自分たちができることから取り組むという姿勢を示した。
行政はごみ処理の方針転換を検討したが、大きな問題は資源化のための産業がほとんど存在しないことだった。
そこで、市内企業の協力を得ながら、リサイクル産業団地の計画を作り、国に働きかけた。これが北九州エコタウンとして、世界最大規模のリサイクル産業団地を実現するきっかけとなった。リサイクル産業は国内だけでなく、アジア各国でも必要となる産業分野であるとの認識が具体化の原動力となった。
しかし、着工段階になって大きな問題が生じた。
市内のごみ処理だけでなく広域から原料となるごみを集めてくることに対して、地元となる地区の住民から不安の声が出てきた。
行政は、企業とともに住民の不安解消のため、時間をかけて話し合いを行った。
最終的には、厳しい監視を条件に、住民の合意を得ることができたが、この時にも、市民、企業、行政の相互信頼関係が生きてきた。PCB処理や震災廃棄物受け入れなど、その後に起きた課題にも、この信頼関係が生きてきた。現在では、様々な環境政策が市民から高い支持を受けて、積極的な参加が得られるようになった。
企業が地域の課題に関心を持って参画すると、地域が発展するということをこの事例は示している。
市民意識の高まりを受けて、廃棄物処理の基本姿勢が見直され、いわゆる処理重視型から資源リサイクル型への転換に取り組んだ。
リサイクル社会を実現するためには、再資源化のための産業と、再生資源の利用・普及が必要となる。これには通商産業省(当時)のエコタウン事業において、全国第1号の認定を受けたことで大きな弾みがついた。
また、再生資源の普及についても、環境教育を始めとするさまざまな取り組みが始まった。
同時に進めたごみ減量化のための指定袋制度を始めとする施策も、市民との対話を重ねて支持を得ることができた。以来、環境政策を実施する上で、市民との対話が基本方針となった。2007年のPCB 受入処理事業を開始できたのも対話の成果である。
(3)環境学習の拠点
環境ミュージアムの第3ゾーンは、子どもたちが、遊びながら環境の重要な概念を学べるコーナー。第4ゾーンは、3Rのコーナー。そして、第5ゾーンでは、市民ボランティアの方々が環境学習のサポーターとして活動している。環境ミュージアムを特徴づける取組である。
2001年、北九州博覧祭が開催された。翌年環境パビリオンを活用して環境ミュージアムが開設され、環境教育活動の拠点が形成された。また、博覧祭を記念してエコライフステージが開催されることとなった。
2008年には「環境モデル都市」に、2011年には「環境未来都市」に選定され、同年には福岡県、福岡市と共同申請した「グリーンアジア国際戦略総合特区」の指定を受けた。北九州市は「環境先進都市・北九州」と呼ばれるようになった。
また、ストックホルム、シカゴとともに、OECDのグリーン成長モデル都市に選ばれ、SDGsモデル都市に選ばれるなど、世界の環境モデル都市となった。
北九州市は、かつては「公害の街」「灰色の街」というイメージで全国に知られたが、現在では「環境先進都市」として国内外に広く知られるようになった。
この間、市民はさまざまな課題に積極的にチャレンジし、これを克服しただけでなく、その過程で得た経験や技術を生かして新たな課題に向かってチャレンジしてきた。現在では、持続可能な社会の実現に向けた先進的な取り組みについて、国内外のモデルとして注目されるようになった。
4 SDGsへの展開
(1)環境首都グランドデザイン
北九州市では、2004年に「環境首都グランドデザイン」を策定した。
市民が実感できる環境首都づくりを目指して、自分たちができること、やりたいこと、あるべき姿について、1000件を超える意見が出された。これらの意見は、3つの柱と10の行動原則にまとめられ具体的な市民グループによる活動が始まった。
それは、SDGsに掲げられた内容とほぼ重なっており、北九州市民は、世界の取り組みを先取りしてきたと言える。
市民の環境活動は、毎年開催される「エコライフステージ」という楽しいお祭りの中で紹介され、環境活動に取り組む人が年々増えている。
1996年策定の「アジェンダ21北九州」は、市の基本構想であるルネッサンス構想の環境版となり、2004年策定の環境首都「グランドデザイン」に引き継がれた。2007年には、環境首都「グランドデザイン」実現のために北九州市環境基本計画が策定された。
(2)環境首都検定
北九州市では「環境首都検定」を毎年1回実施しており、これまでに12回開催した。年々参加者が増えており、前回は5000人を超えた。参加者から「楽しかった。また受けたい」という感想をいただいている。
SDGsの取り組みを考えるとき、地域における環境の歴史を学ぶことにより、たくさんのヒントを得ることができる。環境活動は、楽しくなければ拡がらないし、楽しくなければ伝わらないということを念頭に、協働の輪を広げていきたい。
